
3人目の子どもの妊娠がわかった時、夫婦で話し合い、「この子との時間も、上の子たちとの時間も大切にしよう」と決め、会社の上司へ1年間の育児休業取得を打診しました。最大の目標は、妻の産後の体調を第一に考えること。その結果家族全員が笑顔でいられるように、1年間の育児休業取得を決意し、最終的に育児休業期間は1年1ヶ月に及びました。
育休取得前の不安はゼロではありませんでしたが、結論から言えば、「育休をとって良かったことしかない」です。
9つのメリット:夫婦で乗り越えた育休生活
今回は、育休を1年間とって特に良かったと感じた9つのメリットを、3つの大きなテーマに分けてご紹介します。
子どもたちの成長を間近で見守る喜び 👶
1年間の育休は、子どもたちの「今」を大切にする時間でした。特に赤ちゃんにとっては、1日で驚くほど成長します。
①赤ちゃんの成長を夫婦で分かち合う
粉ミルクを20mlから始めて、最大240mlまで飲めるようになった成長を一緒に見守りました。首が座る、はいはいを始める、初めての一歩を踏み出すといった、かけがえのない瞬間を夫婦で分かち合えたことは、何にも代えがたい喜びです。その瞬間を写真や動画に収めることもできました。
②上の子たちとの特別な時間
6歳の長女は保育園から小学校へ、3歳の次女も保育園生活を満喫。長女の習い事の送迎、翌日の体力を気にせず上の子2人との公園遊びなど、一緒に過ごす時間が増えたことで、子どもたち全員が「パパっ子」になりました。長女の「小1の壁」による精神的な不安定さも、夫婦で協力して乗り越えることができました。家に帰ると両親がいるという安心感は、子どもたちにとってとても良い効果だったようです。次女は「保育園行きたくなぁい」という現象がなく、登園・退園も急かすことなくゆったり過ごすことができました。
③次女のトイトレが育休中に完了
3歳1ヶ月でトイトレが完了しました。早いペースだと聞きますが、1年間かけて取り組んだ結果、おむつが外れた時はとても嬉しかったです。
④小学1年生の壁に向き合う
共働き全世帯が向き合う小学1年生の壁、育休が重なることで、子どもへの安心感が与えられました。そんな小学1年生の長女は毎日放課後楽しそうにし過ごした、また近くで成長を見られたことは親として嬉しかったです。
妻の心と身体を支え合えた安心感 ✨
夫婦共働きの私たちにとって、育休中の家事・育児分担は非常に重要でした。育休中は、授乳以外は極力私がやるというモットーで生活しました。
⑤産後の身体を一緒にいたわる
妻には授乳を中心に生活環境を整えてもらい、夜間の授乳やおむつ替えに早朝で交代するなど、妻がまとまった睡眠時間を確保できるように努めました。産後うつリスクを減らすためにも、夫婦で支え合うことが大切だと感じました。男性も慣れない環境で産後うつになることがあるため、時間を見つけて短時間でも疲れを取るように心がけました。
⑥自由な時間を確保してリフレッシュ
授乳の合間を見て、上の子2人を私が担当する時間をつくり、妻は産後3ヶ月後には週5日ヨガに通うなど、自分の時間を満喫しました。心身ともにリフレッシュできる時間を確保できたことで、妻の雰囲気が明るくなりました。
夫婦の絆がより一層深まる 🤝
育休は、夫婦で「家族のあり方」や「これからの生き方」をじっくり話し合う貴重な機会でした。
⑦家事・育児を一緒にこなす
今まで妻任せだった家事や、お宮参りなどのイベントの段取りにも対応できるようになり、家事・育児・イベントの対応範囲が広がりました。振り返ると、食事や洗濯は私が実施し、妻が空いた時間を子どもに費やしてくれたりと、お互いの時間を有効に使えたように思います。子どもの健康診断や予防接種、風邪を引いた時の病院の付き添いなども含めて、夫婦で対応できたことは良かったです。
⑧ライフプランを話し合う
育休中に家計を見直すのは定石ですが、海外旅行や国内旅行に行った我が家は貯金も使いながらの生活でした。支出は増えましたが、私の「やりたいこと」を達成できました。今後のキャリアについて、将来について改めて考える時間を持てたのも大きな収穫です。
⑨唐突に訪れる不安に向き合う
3人の子どもを育てるという点において、唐突に不安感にかられる瞬間があり、妻と今後どうしていきたいか話し合う機会がありました。この話し合う時間が、夫婦の仲をより深めてくれました。
育休中の苦労と乗り越え方
良いことばかりではありません。育休中は苦労したこともたくさんありました。
特に新生児期の睡眠不足
上の子たちの夜泣き対応と新生児のお世話で、夫婦ともに寝不足の日々が続きました。そんな時は赤ちゃんが寝ている間に一緒にお昼寝したり、家事を手抜きしたりして調整しました。
3人育児はてんてこ舞い
3人の子どもたちに同時に「あれやって!これやって!」とせがまれた時は、正直てんてこ舞いでした。でも、そんな瞬間も子どもが大きくなればなくなるのかなと思って踏ん張りました。
突然くる社会とのつながりがない感覚
仕事をしていると嫌でも誰かと話しますが、育休中は孤独感や焦燥感にかられることがありました。私はX(旧Twitter)で同じ子育てをしている方を見つけて「自分だけじゃないんだ」と気持ちを保ちました。また、生後6ヶ月を過ぎた頃からは友人と会う約束も入れるようにしました。
外部サービスもうまく活用するべきだった
振り返ってみると、自治体のベビーシッター補助制度や産後ドゥーラなどをうまく使えば良かったと思います。何から何まで自分たちだけで解決するのではなく、外部の力を借りることも大切だと感じました。
まとめ:育休は「後悔のない選択」
育休は、決して仕事から離れることではありません。家族というかけがえのないプロジェクトに、夫婦で全力でコミットする時間です。
【知っておきたい育休の制度】
- 育児休業給付金: 育休開始から6ヶ月間は賃金の67%、それ以降は50%が支給されます(上限あり)。これに加えて、社会保険料が免除されるため、手取り額は今までの生活と遜色ない感覚でした。共働きであれば、家計の心配はほとんどなく、貯蓄と給付金を活用して旅行などを楽しむことも可能です。(※1)
- 育児休業の現状: 厚生労働省の調査によると、男性の育児休業取得率は年々上昇しており、令和5年度には30.1%と過去最高を記録しました。しかし、取得期間は「1ヶ月未満」が半数以上を占めているのが現状です。会社の関係者で何名か1ヶ月とったという方はいましたが、1年の育休はなかなかいないようです。(※2)
育休取得を迷っているパパには、ぜひ一歩踏み出してほしいと思います。この経験は、家族の絆を深め、人生をより豊かにしてくれる最高の「投資」になるはずです。
出典
※1:厚生労働省「高年齢雇用継続給付 介護休業給付 育児休業給付の受給者の皆さまへ」
※2:厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」
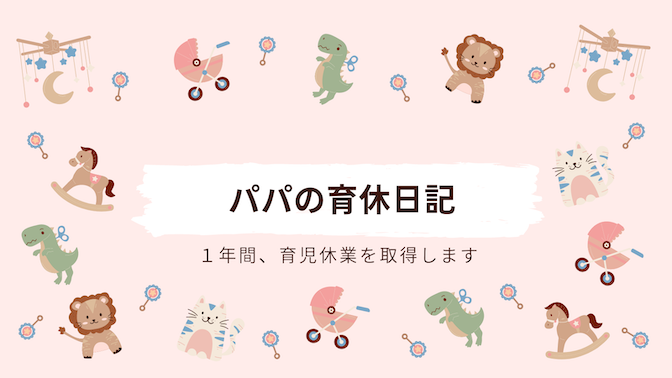
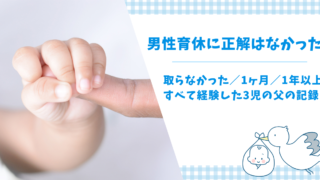
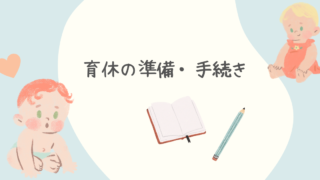

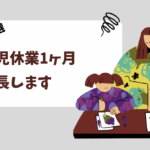
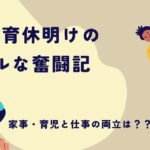
コメント